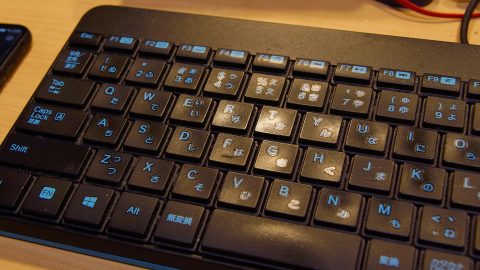写真趣味人がレトロ機を求める理由とかいろいろ

古いカメラをかなり長い期間愛用しているのですが、定期的に「変なものを使っている人がいる」みたいな視線で見られることがあります。単純にカメラに無知・無頓着というのも一因してますし、単純に金銭的事情というのもありますが、趣味としては充分楽しめてます。一周回ってオールドカメラ・レンズの系統は「趣味人の沼」みたいに言われているくらいで「業の深さ」で言えばこっちの方が深淵に近いと思っていますが、実際は「個人の感性の範疇で楽しむもの」なので、私自身は普通に今でも使っている次第です。多機能化著しい映像機器の分野ですが、遡ってフィルムカメラで説明するのであれば「シンプルな深淵」であり、フィルムに記録する写真というのは「知識と経験に基づいた先読みの美学」みたいなものだと思っている次第です。
フィルムカメラのボディはとてもシンプルな構造で構成されており、その機能は「フィルムに決められた時間だけ露光する」のみの構造なので、いかに「昨今のデジタルカメラの類が高機能かつ高性能であるか」というのを痛感する機会が多いです。同時に「写ルンです」という「使い捨てカメラ」が存在する時間軸があったという、映像史実の趣深い歴史の風を感じる機会にも恵まれていると思っています。電池が不要のカメラがあったというのも驚きですし、かつては二眼カメラというのもありましたし、映像の歴史を紐解くのもなかなか趣味として追求しがいのある世界だとも思っています。裏を返せば、昨今のデジタルカメラ機器の「使いやすさ」というのは「温故知新のデジタルデータ化の賜物」でもあるので、触れてみて学んでみるというのも「趣味の深淵に触れる」という意味では重い意味を持ってくるのかも知れません。実際に機材を集めるのは道楽の範疇を逸脱してしまうこと多数ですが、知識として触れてみるのは趣味の知見を深めるためには有益ではないかと考えている次第です。私は先人の写真趣味者たちの話をもっと知りたい。
「写真趣味の定義」に思うこと
趣味の世界はそもそも定義できるものではないと考えている派なので、私自身の括りとしては「手軽かつ安易に記録を残せる」という意味で利用していました。少なくとも「一眼レフの沼地に侵入するまで」は、カメラは記録メディアであり「行動記録データの記録器」くらいの認識でした。カメラ趣味のはじまりがブログメディアの運営に紐ついていたので、カメラの位置付けはそこにあれば充分なものでしたが、かつてマンガやイラストレーターを志していた程度には絵心を持っていたがばかりに「映像を美しく残したい」という願望の絵の具を混入させてしまい、それが現在のカメラ趣味の原点になってしまいました。今はそれをメインで趣味をやっていますし、それで得たものもありますし、なにより「写真撮影を楽しむ意識を自覚した」という意味でとても有意義なものに昇華できたと思っています。「記録を絵画的に捉える」というニュアンスを得たのは、間違いなく一眼レフとの出会いがきっかけでした。
「今見ている瞬間は次の瞬間過去になってしまう」というイメージを持ち、写真趣味を謳歌しています。ただ、はじめて5年くらいは「何となくフルオートでシャッターを切っただけ」でした。「趣味の深淵」を見たのは「沼の片鱗に触れた」のがはじまりで、いわゆる「オールドレンズ」というものに触れたことがきっかけでした。フィルムカメラ時代のレンズにはボディ側からの制御を受け付けない機械式のレンズもあり、それに触れたのがきっかけでマニュアルフォーカスを扱うようになったのが「深淵への招待状」でした。そして、「何故か新しいレンズと遜色の無い映像が出力されてくる」という発見からマニュアルフォーカス主体の撮影スタイルに転向、触れる機会のあるレンズを片っ端から触ってみて研究することになりました。ペンタックス系の機材を使って居たのですが、何故か他メーカーの機器も触るようになり、多様な機材に触れ、沼地の湖底を目指すように深淵の世界に入り込んでしまい、今に至っているのが私の「カメラ遍歴の一端」です。もの凄く激しく拗らせた紆余曲折ですが、私の写真趣味の基幹部分になっている大切な礎になっています。
何を刷り込まれたかというと、ファインダーの向こう側の世界を切り取るという「意思決定権の獲得」であり、「可能な限り自分で決定して映像を切り取る」という膨大なデータの刷り込み。とにかく「フルオート撮影に対して自分の回答を出す」という行動規範みたいなものを徹底に仕込まれました。言ってしまえば「機械任せで出力された映像」と「自分の感じたイメージ映像」を天秤にかけ、限りなく自分のイメージに近い映像を出力させる「映像哲学」みたいなものを学びました。哲学と表現したのは「模範例」はあっても「唯一の回答が無い」という意味合いを多大に含んでいるから、と位置付けています。
「撮れる理由」を考えたことがあるか
先人の諸先輩の方々から「フィルムカメラ時代の苦労談」を聞かされる機会がありましたが、「今より扱いの厳しい機材で撮れるんだ」という事実を受け止めるという行為に繋がっており、現在も使っている旧式の一眼レフは今なお「優秀な訓練機」としての立ち位置を確立しています。かつての35ミリフィルムは画像素子に換算すると「億画素」級のものという話ですが、フィルムは非常にデリケートな素材なため、保管庫が必要な程度に苦労する記録メディアでした。また、現像工程に於いても一定の誤差は出てしまう程度に敏感なもので、出力する機器によっても誤差は出てしまったという話を聞いたことがあります。そういえば専門のフィルム売場って冷蔵庫みたいなところに陳列されていたような記憶があったような無かったような。あと、感光素子であるため「暗室が必須環境」で「現像液の廃液が産業廃棄物」という話も、フィルムカメラの「クセの悪さ」として語り継がれているとか何とか。「フィルムは生もの」って言われていたそうです。
プレビューがその場で確認出来なかった時代にも「記憶に残る写真」が遺っているという事実は、旧式カメラでも撮れるという確信として今なお基礎となっています。同じ風景をほぼ同じ映像として撮影した際、カメラの年式や装着レンズによって撮影の解釈が劇的に変わるというのはとても興味深い経験でした。その先にあるのは底無しの趣味人専用の沼なのですが、これこそが趣味人が趣味人として得られる希少な栄養なんだなというところまで考えが届くようになったのも事実です。「何故その風景がそう撮れるのか」が瞬時に機械的な理解ができると、写真趣味の懐が劇的に深くなる。これが解るようになると機械式のマニュアルレンズなどの「キワモノのオールドレンズ」が扱えるようになるので、趣味としてのカメラが恐ろしく深い沼のように感じられますが、「それが楽しくなってしまう」という病的な快楽要素を得られるようになってしまいます。結果として、今めちゃくちゃ楽しいのは間違いなく事実なので。
趣味とは「生涯を賭せる学術的快楽」という認識です。生涯にひとつ、一生を賭けられるような熱量を持ったことができれば、人生は劇的に楽しいものになるのではないかと思う次第です。めちゃくちゃ拗らせた紆余曲折を経て得たのは「古い機器で相応にキレイに撮れる技術」でしたが、同時に「新しい機材ではもっとキレイに撮れる技術」でもありました。もう何周もまわって新しい機材の事で拗らせていますが、今は最新機種を買うお金がありません。もうしばらくは現状維持にしがみ付く予定。
趣味人の辿り着く場所とは
もうひとつ、「趣味は伝承するもの」というのが私の内側にはあります。自己満足で解決する趣味も多種ありますが、趣味を加速させ満足度を高めるにはやはり「同好の士」の存在が不可欠だと思っています。また、趣味の理解や俯瞰図を得るためにも、さらには自身の自己成長のためにも他者の存在は尊重すべき部分であると考えています。よって、「趣味を材料にしたコミュニケーション構築」は、コミュニケーション簡略化の著しい昨今においては技術以上に重要視すべき部分ではないかと考えている次第です。技術は意外と簡単に伝承される部分であったりするのですが、人的な交流などの内面的な部分はなかなか伝承されないケースが多く、昨今は重大な人的トラブルに発展するケースも複数観測されているという話。より良い趣味環境のために必要なのは「良い機材」以上に「良い倫理環境」というのは、昨今のトラブルに学ぶべき事案だと思っている次第です。ルール無きスポーツみたいになっいると揶揄する人もいるとかで、昨今は複数人で写真趣味とは言いにくくなった感があります。写真趣味に関しては特に「円滑な共存関係の構築」が無いと本当にやりづらい部分が多いので。
写真系のソーシャルメディアでも迷惑情報の観測数が増えてきたと言われており、一部のジャンルの写真界隈では危険行為に至った事例もあったとか。こうなってくると「カメラそのものが規制対象になる可能性」というのが取り沙汰されてしまうので、技術伝承以上に倫理教育の伝承が急務になりそうではあります。どちらかといえば「これからも趣味を楽しめるものとして維持するために」っていうニュアンスがあってやりにくいのですが、昨今の趣味界隈は本当に「片道通行なコミュニケーション」が頻発しているように感じます。昔教わった趣味人の振るまいというのは「共に切磋琢磨し高みを目指す」とか「良い社会環境のための交流手段」などの多様な側面があったと聞いてきましたが、ここ数年は「自己主張のための手段」や「優位性を得るための行為」になってしまった感が否めません。ごく一部の迷惑人のために「同好の士が団結する」というのはいささか方向性の違いが見え隠れしてしまうのですが、趣味人が趣味を守る手段として行使せざるを得ないという状況の醸成が背景にあり、昨今趣味に打ち込みにくいという話になってきています。「義務教育の敗北」というのがあるのであれば、それは知能指数がどうとか学習成績がどうとかそういう問題ではなく、「コミュニケーション能力の低下」や「慢性的な協調性不足」とかの方かと思ってしまいます。人のことを言えるほどコミュニケーションは上手くは無いですが、法的に倫理観アウトなことはやってないとは自負できる程度には頑張っているつもりです。
趣味は「人を豊かにする心的材料」であり、いかなる趣味であっても「冒涜してはならない要素」であると、私は結論付けたい。多様な趣味に触れ、色々な思想や思考に触れてきましたが、心的余裕の無い趣味活動はもう「趣味と呼べるものではない」と思う次第。写真趣味社をカメコと蔑みたくはないし、オタク趣味を言葉の暴力等で侵害もしたくない。結局は少しでも長く趣味活動を続けたいだけなのですが、願わくは「趣味の在り方を考えられる人」で在り続けたい。「10年後も安心して今と同じ趣味を維持できれば」という気持ちの下に今の趣味活動を行っています。社会がどれだけ荒んでいるかは、ソーシャルメディアを見ればだいたい把握出来るという話。「ソーシャルメディア」だけに。
趣味の主成分は「思いやり」という話は、あながち間違ってないように思う。そんな昨今の頭痛のタネ。これを書いているっていうことは、私も大した心的余裕は無いのかなって思ったり。